※本記事は、客観的分析のため『だ・である調』で統一しています。
【渋幕中2026解剖】大問1に隠された「解と係数の関係」。“約数パズル”の皮を被った数学である。
序論:仮説の再確認
先日実施された2026年度・渋谷教育学園幕張中学校(一次)入試。その問題を分析すると、今年もまた、渋幕算数の本質が浮き彫りとなる構成であった。
一見すると「数のパズル」や「積み木の作業」に見える問題群の背後に、より抽象度の高い思考(数学的な構造)が埋め込まれている。
本稿では、象徴的な3題を取り上げ、「算数として処理しても解けるが、数学として見るとその正体が透ける」という観点で解剖する。
1. 【大問1】数の性質:正体は「解と係数の関係」
今年度の大問1は、次のルールで定義されている。
2つの整数の積が $A$ であるとき、カード $A$ は、その2つの整数の和が書かれた箱に入っています。
例として、$9 = 1 \times 9$(和10)、$9 = 3 \times 3$(和6)より、カード9は箱10と箱6に入る。
多くの受験生はこれを「約数と和のパズル」として処理しただろう。もちろん、その処理で正解は出る。
しかし、高校数学の視点で見ると、この操作は「2次方程式の解と係数の関係(ヴィエタの公式)」と同型である。
2つの数を $\alpha, \beta$ とすると、これらを解とする2次方程式は次の形になる。
$$x^2 – (\alpha + \beta)x + \alpha \beta = 0$$
ここで、定数項 $\alpha \beta$ が「カードの数(積)」に対応し、1次の係数 $\alpha + \beta$ が「箱の数(和)」に対応する。
つまり大問1は、「積(定数項)が与えられたとき、和(係数)がどう動くか」を整数範囲で追跡させるシミュレーション問題になっているのだ。
特に(3)の「ちょうど5個の箱に入っているカード」を探す設問は、単なる作業ではない。
「因数分解の型(積の表し方)が何通りあるか」を論理的に逆算する発想が求められる。
結局、ここで問われているのは「掛け算 $\to$ 足し算」という表層の計算力ではない。条件を数学的な構造として捉え直す力である。
2. 【大問2】場合の数:論理的「全探索」をやり切る覚悟
大問2は、6つのマスに1〜4の数を入れる配置問題である。
条件として「和が等しい」「積が等しい」などが課されるため、公式一発で片付く問題ではない。
ここで重要なのは、まず「等しくなる値」を $T$ と置いて、可能性の範囲を先に潰すことだ。
例えば(1)で、「ア・イ・ウの和」「エ・オの和」「カ」がすべて等しいなら、その共通値は $T = \text{カ}$ である。
マスに入る数は1〜4なので、$T$(すなわち和)の最大値も「4」に制限される。
この時点で候補は激減する。あとは手を動かして全探索すればよい。
ここで求められるのは、「範囲(Range)を絞り、残った候補をしらみつぶしに検証する」という研究者の姿勢である。
「何か便利な公式があるはずだ」と待ち構える受験生ほど、この泥臭い検証を避けて時間を失い、自滅する。
渋幕はこの種の問題で、受験生の「思考の態度」そのものを選別している。
3. 【大問5】立体図形:空間を“分割して足す”発想
大問5は、のり面を持つ立方体(K)を組み合わせ、切断する問題である。
(3)では中点P、Qを通る平面で切断し、さらに立体を分解して個数・体積を問う。
ここに「作図テクニック」だけで挑むのは危険だ。有効なのは、やはり「空間を情報として捉える視点」である。
- 立方体を単位空間(グリッド)として見る。
- P、Qの位置を“点の情報(座標)”として固定する。
- 切断面がどこを通るかを、分割のルールとして整理する。
そうすれば、最後は「複雑な立体」を「基本単位」に分け、その総和を取るだけの作業になる。
これは、数学(積分法など)の基礎にある「分割 $\to$ 合計(区分求積)」の思考プロセスそのものである。
結論:2027年以降の受験生へ
2026年の渋幕算数も、例外なく「脱・算数」の構造を保っていた。
平均点や難易度の数値だけに惑わされてはならない。重要なのは、以下の3つの能力が問われているという事実だ。
- 翻訳力:独自ルール(大問1)を、式・表・構造へ変換する力。
- 実験力:候補を絞り込み、手を動かして検証する力(大問2)。
- 空間認識力:立体を分割のルールとして扱い、論理的に数える力(大問5)。
これらは、中学入試の枠を越えて、将来の大学受験数学における「難問処理」の土台となる。
渋幕合格を狙うなら、「算数の上手さ」だけで完結させてはならない。
算数という道具を使って、数学的な探究を実行できるか。そこが合否を分ける唯一の分岐点になる。






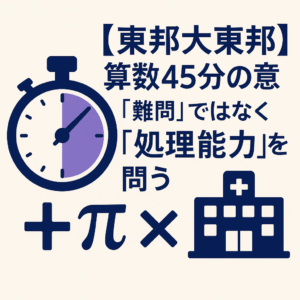
コメント